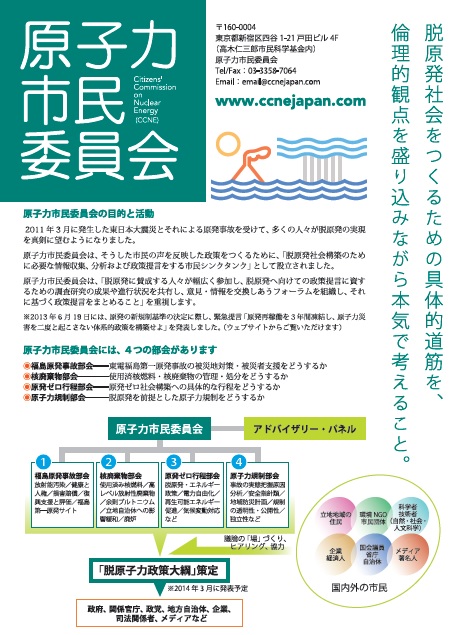|
2025年2月18日
声明:除去土壌の「復興再生利用」は、放射能に汚染
された土の無秩序な拡散につながり、許されない
―省令案は趣旨が変質しており、改正の正当性がない
原子力市民委員会
座長 大島堅一
委員 後藤 忍、後藤政志、清水奈名子
茅野恒秀、松久保肇、武藤類子、吉田明子
1.「省令案」への原子力市民委員会の意見
環境省は、福島第一原発事故後の除染作業で発生した除去土壌(放射能に汚染された土壌)を全国の公共事業等で「復興再生利用」するため、放射性物質汚染対処特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等について、2025年1月17日から2月16日の一カ月間、意見募集(パブリックコメント)をおこなった。原子力市民委員会は、下記の論点にもとづく8つの意見を提出した(詳細は後述)[1]。
【意見1】 除去土壌の再生利用(復興再生利用)には法的正当性がない。
【意見2】 除去土壌は被ばくのリスクが高く「再生利用」してはならない。
【意見3】 除去土壌の再生資材化は放射性物質・放射性廃棄物の取り扱いに関する二重基準である。
【意見4】 除去土壌は低レベル放射性廃棄物として扱い、浅地中処分する必要がある。
【意見5】 環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない。
【意見6】 長期管理の責任、方法、基準がない、もしくは曖昧である。
【意見7】 IAEA報告書は「復興再生利用」を正当化するものになっていない。
【意見8】 利害関係者との協議についての定めがない。また公聴会等広く意見を聞く機会も設定していない。
2.前回の省令改正見送り時に指摘された問題は解消されていない
原子力市民委員会は2019年5月に声明「環境省は除染土の再生利用と安易な処分をやめ、国民の熟議と合意にもとづいた最終処分のあり方を提示せよ」[2]、2020年2月には声明「環境省は放射性物質の無秩序な拡散につながる除去土壌の再生利用方針を撤回し、事故由来放射性廃棄物・除去土壌の体系的な最終処分のあり方を再構築せよ」[3]を発出している。
2019年の声明は、各地で「実証事業」の問題が噴出している中で省令案・ガイドライン案の策定が進められていることに警鐘を鳴らすものであった。2020年の声明は今回の省令案等と性質を同じくする省令案・告示案が当時示されたことに対する意見として提出したものである。2020年の省令案・告示案には2,800件を超えるパブリックコメントが提出され、そのほとんどが反対意見であった。その後、環境省は明確な理由を示さないまま「現時点では制定しない」として改正が見送られた。このような事態はきわめて異例のことであるが、省令改正が多くの問題点を孕んでいたことの証左と言えよう。
2020年の省令改正見送りから5年の間、環境省は「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」とそれに連なるワーキンググループやチームで検討を続けてきた。しかし2019年から2020年にかけて、原子力市民委員会だけでなく多くの市民、団体、研究者らから指摘された問題群は、今回の省令案で何ら解消されていない。
3.省令案が福島県外の除去土壌の再生利用も対象とすることは、国民に一度も説明されていない
今回の省令案の公表後も、環境省は「説明会や公聴会の開催予定はない」との姿勢であったため、1月30日、2月6日には超党派国会議員連盟「原発ゼロ・再エネ100の会」会合において、また、2月14日には原子力市民委員会と放射能拡散に反対する会が主催した「放射能の拡散につながる「除去土壌の再生利用」問題に関する緊急市民“公聴会”」において、環境省を招くかたちで質疑をおこなった[4]。その結果、参加した市民や専門家、国会議員が指摘した省令案等が有する問題を払拭できる回答を環境省から得られなかったのみならず、2月14日の緊急市民“公聴会”では、省令案等からは到底読み取ることのできない新たな事実が判明した。すなわち、再生利用の対象となる除去土壌は、福島県内の中間貯蔵施設にあるもののみならず、福島県外に保管されているものも含まれるということである。
復興再生利用の実施者に関する市民からの質問に答える中で、環境省は「省令案第58条4の第2号イの事業実施者について、環境省の他に地方自治体を事業実施者として想定している」と説明した。これは、今回の省令改正によって、福島県外における除染により発生した除去土壌も「処分の一環としての再生利用」が可能になるということを意味する。
そもそも除去土壌の再生利用という方針は、中間貯蔵施設に搬入された除去土壌の県外最終処分に向けた取り組みの中で、2016年の時点で最大約2,200万m3と推計された全量をそのまま最終処分することが「実現性が乏しい」という事情から、「本来貴重な資源である土壌」という詭弁を弄して打ち出されたものである(『中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略』)。
福島県外の除去土壌は「各県処分」の考え方のもとに、環境省も「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」とは別に「除去土壌の処分に関する検討チーム会合」を設置して検討を重ねてきた。ところが今回の発言を受けて改めて調べたところ、2024年10月3日、2019年3月以来5年半ぶりに「環境回復検討会」が「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会」との合同会合という形で招集され、福島県外の除去土壌も再生利用することが環境省から説明されていた。当日の議事録によれば、「福島県外につきましても、今保管されている仮置場等の解消を図るために、再生利用・埋立処分を行うことが必要である」と、「処分の一環としての再生利用」どころか、再生利用が優先であるというような説明が環境省からなされていた。こうした姿勢は、到底看過しがたい。
これまで国民には「中間貯蔵施設に搬入された除去土壌の県外最終処分に向けた対策としての「再生利用」」と説明してきた。しかし、今回の省令案ではこの趣旨が変質している。この省令案が福島県外の除去土壌の再生利用も対象とすることは、国民に一度も説明されていない。これらの点からして、省令改正そのものに正当性がないと認識せざるを得ない。環境省は省令改正を改めて見送り、本声明が下記で表明する意見をとりいれるべきである。
記
原子力市民委員会の「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案等」に対する意見
(意見には、原子力市民委員会が放射能拡散に反対する会と共同で2025年1月15日に開催した緊急オンライン・リレートーク「放射能に汚染された土の無秩序な拡散につながる『除去土壌の再生利用』はありえない」の講演資料[5]も添付した)
【意見1】 除去土壌の再生利用(復興再生利用)には法的正当性がない。
省令案第58条の4は、除去土壌の「復興再生利用」が特措法第41条第1項の「処分」に含まれるとしている。しかし東京電力福島第一原発事故後に原子力安全委員会が示した考え方では、廃棄物の再利用と処理・輸送・保管、そして処分は明確に分けられる。また循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(同法第2条2項1号では「処分(再生を含む。)」とあえて説明をつけている)など他の環境法令でも、「処分」と「再生」「再利用」「再生利用」などの概念は明確に分けられている。土壌汚染対策法においても「浄化」はあるが「再生」の概念は存在しない。法律の条文に記載がないまま、再生利用(復興再生利用)を「処分」の一環と強弁することは、他の法令における諸概念との整合性を欠いており、法の恣意的な拡大解釈と言わざるを得ず、許されるものではない。
【意見2】 除去土壌は被ばくのリスクが高く「再生利用」してはならない。
省令案第58条の4第1号ホの規定に基づく告示において、セシウム134とセシウム137を合わせて8,000ベクレル/kg以下の除去土壌を復興再生利用に用いることができるとしている。関連資料の「復興再生利用に係るガイドライン(案)」では、8,000ベクレル/kg以下の除去土壌の場合、外部被ばくが0.93ミリシーベルト/年であり、1ミリシーベルト/年に満たないとしている。
これは1ミリシーベルト/年未満になるようにさまざまな条件を仮定して計算した辻褄合わせに過ぎない。環境省の計算方法を検証した黒川眞一氏(高エネルギー加速器研究機構名誉教授)によれば、500m×500mの広さ、高さ4.5mの除去土壌を盛土した場合、8,000ベクレル/kg(8ベクレル/g)の除去土壌に被ばく線量評価値1.89×10-1マイクロシーベルト/時間の係数を掛けると1.512マイクロシーベルト/時間となる。これは13.2ミリシーベルト/年となる値で、1ミリシーベルト/年を遙かに上回る被ばく量である。環境省は、作業時間を1,000時間/年とすることで1.51ミリシーベルト/年とし、さらに3m×12m×2.2cm(厚さ)の鉄板を敷いて得られる減衰率0.6を掛け、ようやく0.93ミリシーベルト/年という値にしているのである。
また、環境省は8,000ベクレル/kgという濃度は10,000ベクレル/kgより小さいので、電離放射線障害防止規則(電離則)で定義された放射性物質ではないと主張しているが、上の例の盛土の場合の線源の総ベクレル数は最大20兆ベクレルに及び、線源の強さは電離則の想定するスケールを遙かに超えている。電離則は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令によって定められている。すなわち労働者を被ばくから守るための規則である。にもかかわらず、作業条件に仮定に仮定を重ねて電離則の対象外とし、「再生資材化した除去土壌の利用に係るガイドラインのポイント(案)」で、施工時の留意事項として「施工や災害等の復旧に当り、特別な防護措置を要することなく、通常の作業の範囲内で対応できる」としている。これは再生利用(復興再生利用)に従事する労働者の安全をないがしろにしていると言わざるを得ない。
また実際には、中間貯蔵施設での掘り起こし(掘削)から積載、輸送、荷下ろし、搬入・仮置き、再生資材化、積載・搬出、現場施工という再生利用(復興再生利用)の全工程で、放射性物質に汚染された土壌の粉塵・微少粉塵が発生し飛散するので、現場作業員や近隣住民には吸引による内部被ばくのリスクがある。環境省のワーキンググループで議論されているように、8,000ベクレル/kgの除去土壌はクリアランスレベル(100ベクレル/kg)にまで減衰するのに190年もの時間がかかる一方、土木構造物の耐用年数は一般には70年程度とされる。再度の工事が必要になる時点でも被ばくのリスクが変わらずある、ということである。それだけでなく、災害に見舞われその復旧に従事する作業員が、上述の鉄板などの整った環境で作業できる保証はない。
【意見3】 除去土壌の再生資材化は放射性物質・放射性廃棄物の取り扱いに関する二重基準である。
省令案第58条の4で定める復興再生利用の実施に関して、原子炉等規制法においては、セシウムの放射性濃度100ベクレル/kg~8,000ベクレル/kgの土壌は低レベル放射性廃棄物として扱われ、低レベル放射性廃棄物として処分される。低レベル放射性廃棄物の場合、電離則でいうところの放射性物質とみなされないものも含めて、厳しい基準に基づき、原子力規制委員会によって認可された上で、専用施設で保管、管理され、特定の施設で処分される。仮に濃度が電離則に定められた値より小さくとも、電離則が想定するスケールを超える量と強さを持つものについては、厳しい基準の下で防護措置をとりながら適切に処分される必要がある。
しかし環境省は、福島県内の除去土壌を全て県外最終処分することは「実現性が乏しい」ため、「土壌は貴重な資源」(『中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略』)と言い、「復興再生利用」を、福島県を含む全国各地で進めようとしている。本来、低レベル放射性廃棄物として専用施設で処分されなければならない除去土壌が、道路工事の路盤材等に「再生資材」として利用されるという事態は、原子炉等規制法にもとづく取り扱いと比べ、きわめて恣意的かつ無責任である。意見1で述べたとおり、特措法で定める除去土壌の処理には「収集」「運搬」「保管」「処分」しか存在しないことをふまえれば、環境省は法令を誤って解釈し、「低レベル放射性廃棄物」と「再生資材」という二重の取り扱い基準を作り出していると言わざるを得ない。
【意見4】 除去土壌は低レベル放射性廃棄物として扱い、浅地中処分する必要がある。
省令案第58条の4で定める復興再生利用の実施に関して、原子炉等規制法またIAEAの安全基準に照らしても、除去土壌は低レベル放射性廃棄物である。環境省自身も中間貯蔵施設における除去土壌等の減容化技術検討ワーキンググループにおいて「IAEA安全基準における分類上は低レベル放射性廃棄物に該当するものと考えられる」と説明している(2024年1月12日、第4回、資料3-1「除去土壌等の最終処分に関する安全確保について(第3回IAEA専門家会合に向けた考え方の整理)」)。
このことからすれば、除去土壌等は、原子炉等規制法における規制と同様、100ベクレル/kg以上を基準にクリアランスの可否を判断し、クリアランスレベルを超えるものは低レベル放射性廃棄物として処分すべきである。なお主要国で、道路等、人が利用するインフラの下で低レベル放射性廃棄物処分が実施されている事例はない。
【意見5】 環境省が事業者と規制者の双方の役割を重ね持ってはならない。
省令案等全体を通じて、環境省は除去土壌(低レベル放射性廃棄物)の再生利用を実施する「事業者」としての役割をもつ一方、これを管理・監督する「規制者」の役割を同時に持とうとしている。これは、放射性物質の取扱いに関するIAEA基準(規制機能の事業実施機能からの独立)(SF-1, GSR Part 1 要件4, GSR Part 3)から明らかに逸脱している。これも、放射性物質の取扱いに関する二重基準であり、是正されなければならない。
環境省が事業者と規制者の二重の役割を兼ねてしまっているがゆえに、本来、低レベル放射性廃棄物処分場で処分されなければならない除去土壌を、全て県外最終処分することは「実現性が乏しい」ために「土壌は貴重な資源」と位置づけてその利用をはかるという倒錯した事態が起こっているのではないだろうか。
IAEA専門家会合最終報告書は「安全性を保証するためには、規制当局の独立性が重要である」(p.34)と指摘している。環境省内で、除去土壌の「再生利用」にあたって規制と事業の担当を分けるのだと説明したとしても、これには無理があり、国民にも理解されない。同じ省内で規制と事業を分離するのは不可能である。同じ省庁で、規制と事業が併存できないのは、経済産業省の下におかれた原子力・安全保安院が廃止され、独立した原子力規制委員会が設置されたことからも明らかである。
なお本年1月30日の「原発ゼロ・再エネ100の会」会合において環境省の担当者は、規制と事業の独立に関して必要性を認識しており省内で検討中、と回答した。そうであれば、省令案等は規制機関の独立化を実現してから、その規制機関によって提案されるべきだろう。今回の環境省による省令改正自体に正当性がないと言える。
【意見6】 長期管理の責任、方法、基準がない、もしくは曖昧である。
環境省は「復興再生利用に係るガイドライン(案)」を示している。このガイドラインは2020年の省令改正時に案がまとめられていた「福島県内における除染等の措置に伴い生じた土壌の再生利用の手引き(案)」の改訂版と言って差し支えないもので、当時もこの「手引き(案)」に法的拘束力がなく、単なるガイドラインに過ぎないことを指摘した。今回の省令改正では名称もまさに「ガイドライン」となり、どの程度の拘束力・実効性があるのか、明確でない。
とくに省令案第58条の4で定める測定や記録等の情報の保管期間は「復興再生利用の終了するまで」としているのみで、管理終了期間が定められていない。「復興再生利用の終了するまで」とは、どの程度の期間を指すのか、「ガイドライン(案)」でも「今後環境省において整理を行う」となっているだけである。前回の意見募集から5年の間、環境省は何を検討してきたのかと疑問を持たざるを得ない。
こうしたルールが科学的根拠にもとづき明確にできないのであれば、除去土壌の復興再生利用は事実上の最終処分と捉えられうる。
【意見7】 IAEA報告書は「復興再生利用」を正当化するものになっていない。
国際原子力機関(IAEA)は、2023年5月から2024年2月にかけて除去土壌の再生利用等に関する専門家会合を開催し、2024年9月に「IAEAから環境省への『福島第一原子力発電所事故後の除染活動で発生した除去土壌の減容・再生利用』に関する支援・専門家会合最終報告書」を環境省へ提出した。
この報告書で専門家が参照したのは、除去土壌の「再利用」ではなく「廃棄処分」に関する基準である(濱岡豊「IAEA汚染土減容・再利用専門家会合最終報告書の問題点」、2025年1月15日緊急オンライン・リレートーク資料)。IAEAの専門家に対して、日本政府は放射線防護の前提である「正当化」「最適化」のいずれも定量的な評価結果にもとづく情報を提供しておらず、IAEA報告書は日本政府の「福島の復興が優先課題」「除染がリスク低減に寄与した」などの説明を正当化の根拠としているのみである。
同時に「最適化」についても問題がある。最適化とは経済的・社会的要因を考慮し、合理的に達成可能な範囲で被ばく線量を低減すること(ALARA)を、ステークホルダーが参加して決めるというものである。IAEA報告書にも「最適化の取組を通じて目指すべき線量水準は、地域住民や自治体などのステークホルダーと相談して決定されると認識している」とある。しかし、環境省はそのような合意形成努力を怠っている。
このような日本政府の情報提供と、それに基づくIAEAの専門家会合報告書を「お墨付きを得た」というニュアンスで説明するのは、誇張に他ならず、不適切である。
【意見8】 利害関係者との協議についての定めがない。また公聴会等広く意見を聞く機会も設定していない。
IAEA報告書には「目指すべき線量レベルは地域住民や市町村などの利害関係者と協議して決定することを制度に明記する」と書かれている。にもかかわらず、省令案等には、地域住民、市町村等の利害関係者との協議についての定めが一切ない。あるのは事業実施者と「復興再生利用に係る施設若しくは工作物を管理する者又は当該復興再生利用を行う土地を管理する者」との協議のみである(第58 条の4 の2)。
今回、環境省が打ち出した「復興再生利用」は除去土壌の再生利用を全国規模で広げていくためのものである。にもかかわらず公聴会も説明会も実施していない。理解醸成活動と称した一方的な広報活動だけである。「復興」「再生」という言葉をひたすら強調し、クリアランス基準を超える汚染土壌が生活環境の近傍での工事等に使用されることに伴うリスクの存在を十分に説明しないまま、「復興再生利用」が強行されてはならない。省令改正で済ませず、法律で明確に定めるべきものであり、国会での審議に諮るとともに、公聴会を各地で開催するなどして広く意見を聴取すべきである。
以上
[1] 本声明では法律に定められた用語としての「除去土壌」を用いるが、本来は放射性物質によって汚染された土壌であることに鑑み、汚染土、放射能汚染土、あるいは除去放射性土壌のように呼ぶべきものである(報道等では「除染土」と呼ばれることもあり、原子力市民委員会の2019年の声明でもこの用語を使ったが、放射性物質を取り除いた(除染された)土壌のように誤解されるので適切ではない)。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」は「特措法」と省略して記載する。
[2] https://www.ccnejapan.com/?p=9951
[3] https://www.ccnejapan.com/?p=10796
[4] https://www.ccnejapan.com/?p=15995
[5] https://www.ccnejapan.com/?p=15948
本件についての問い合わせ先:原子力市民委員会 事務局
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町16-16 iTEXビル3F
(高木仁三郎市民科学基金内)
TEL: 03-6709-8083
Email: email@ccnejapan.com
|

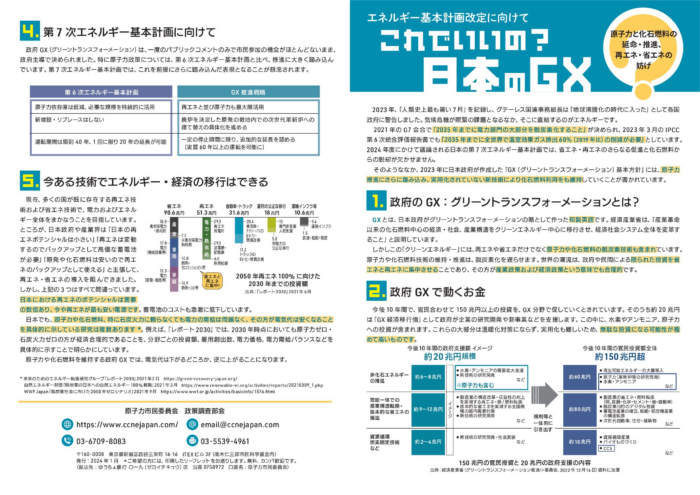
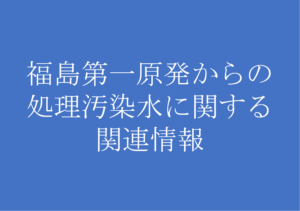
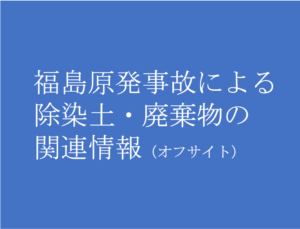
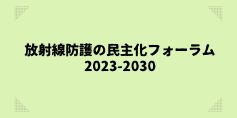
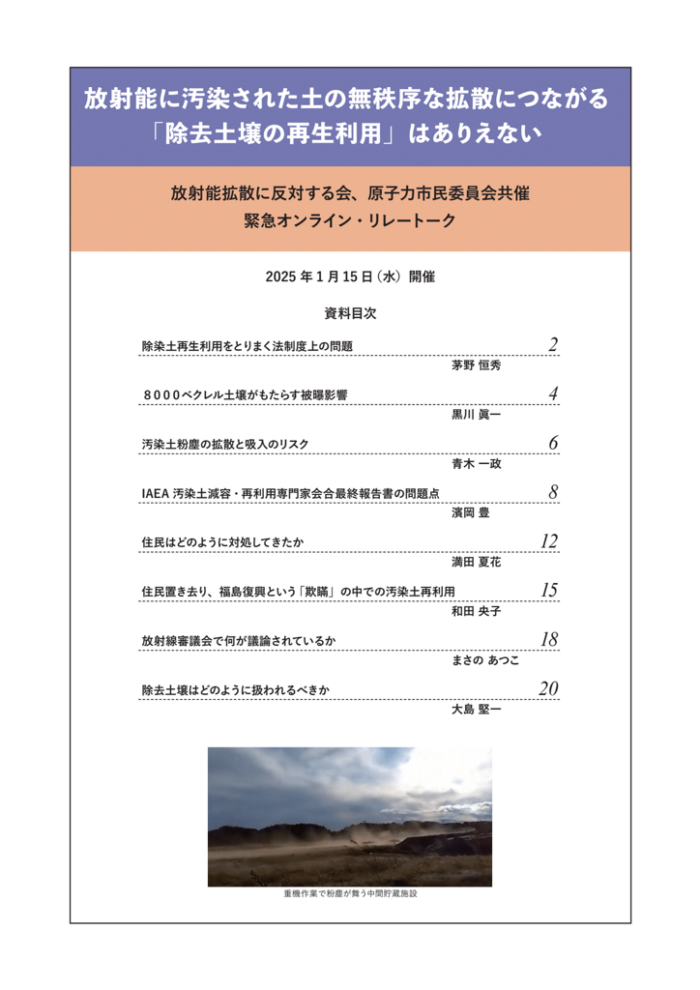
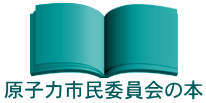
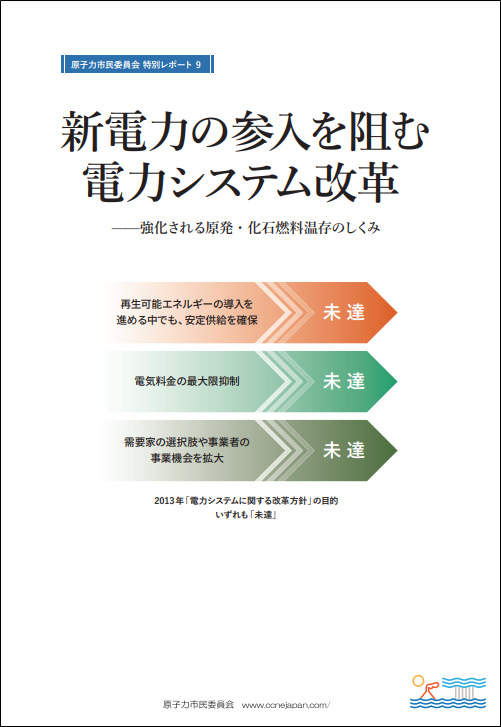
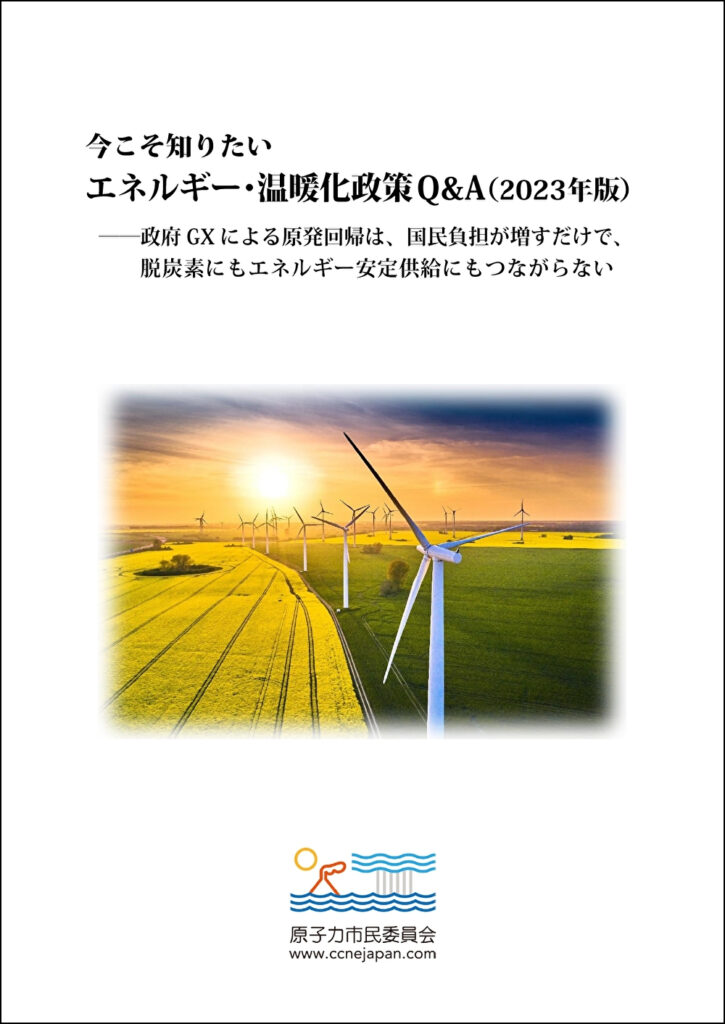
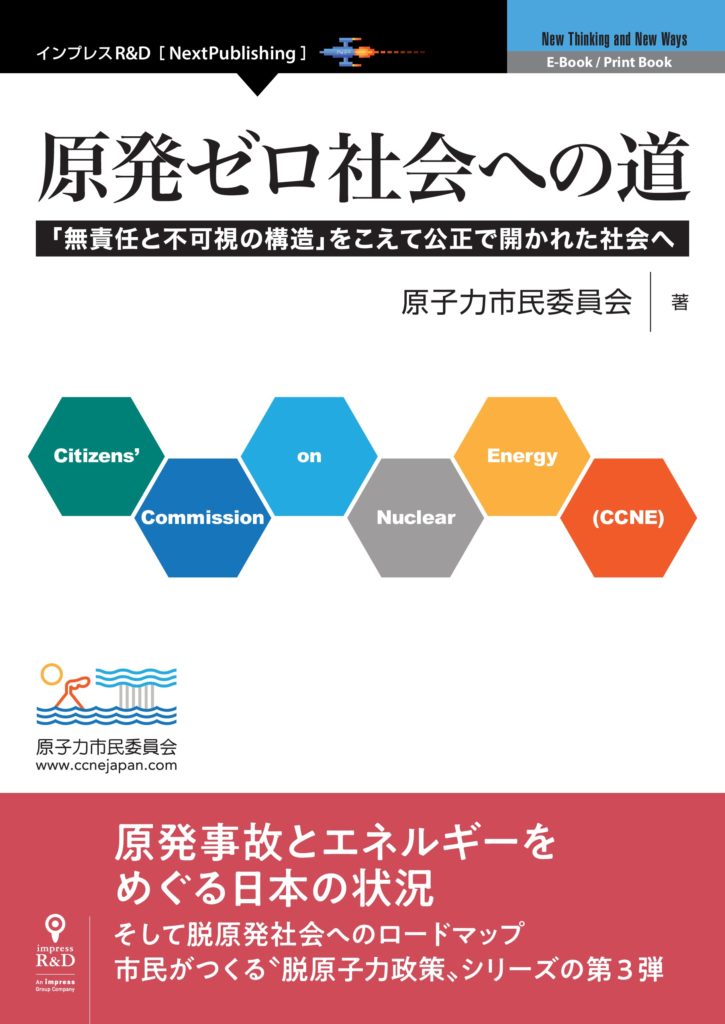
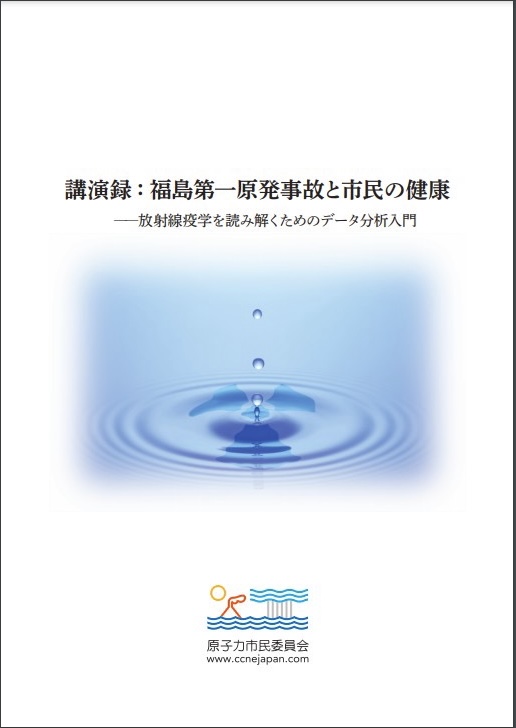
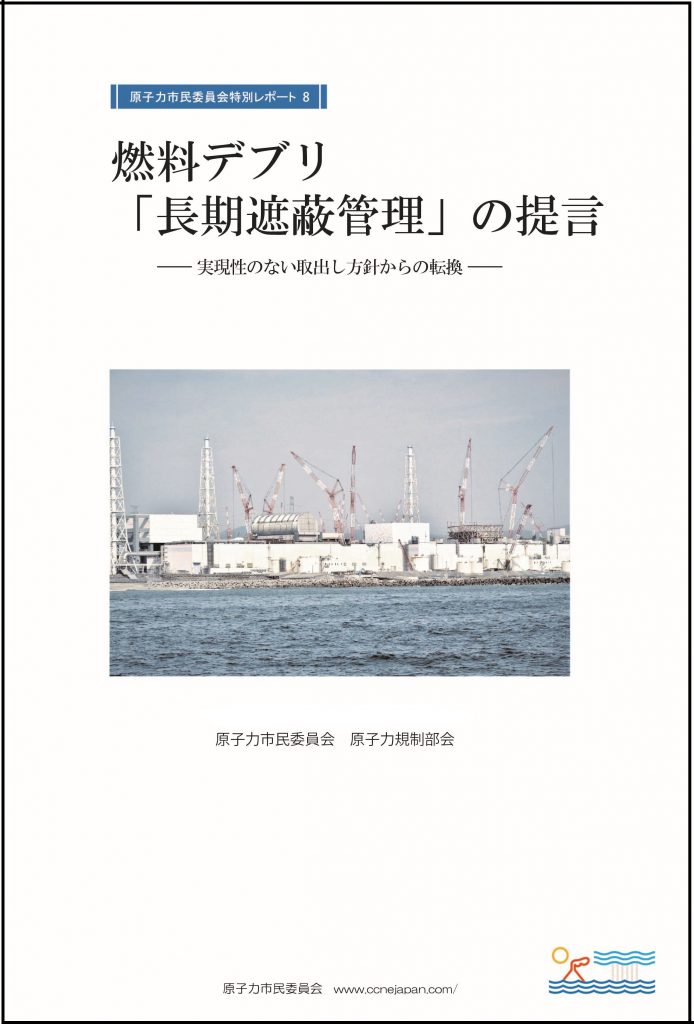
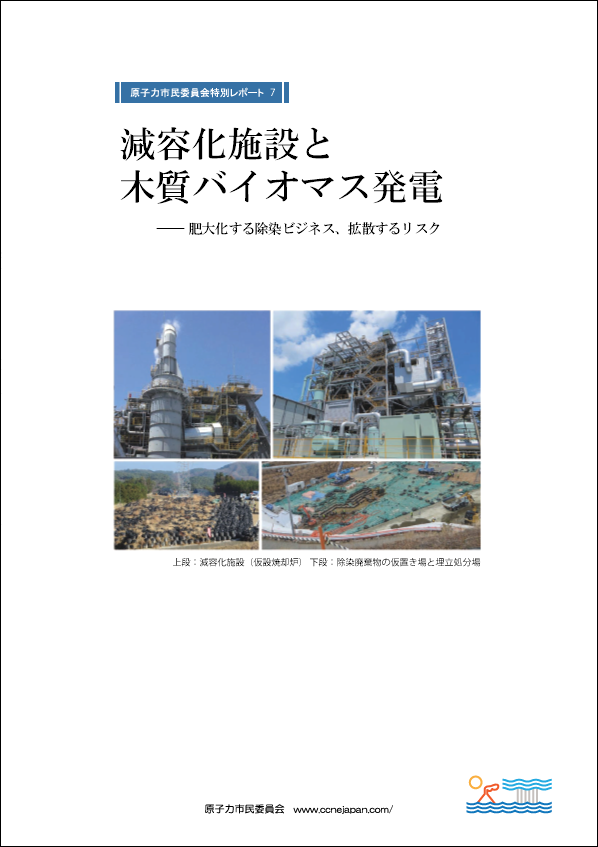
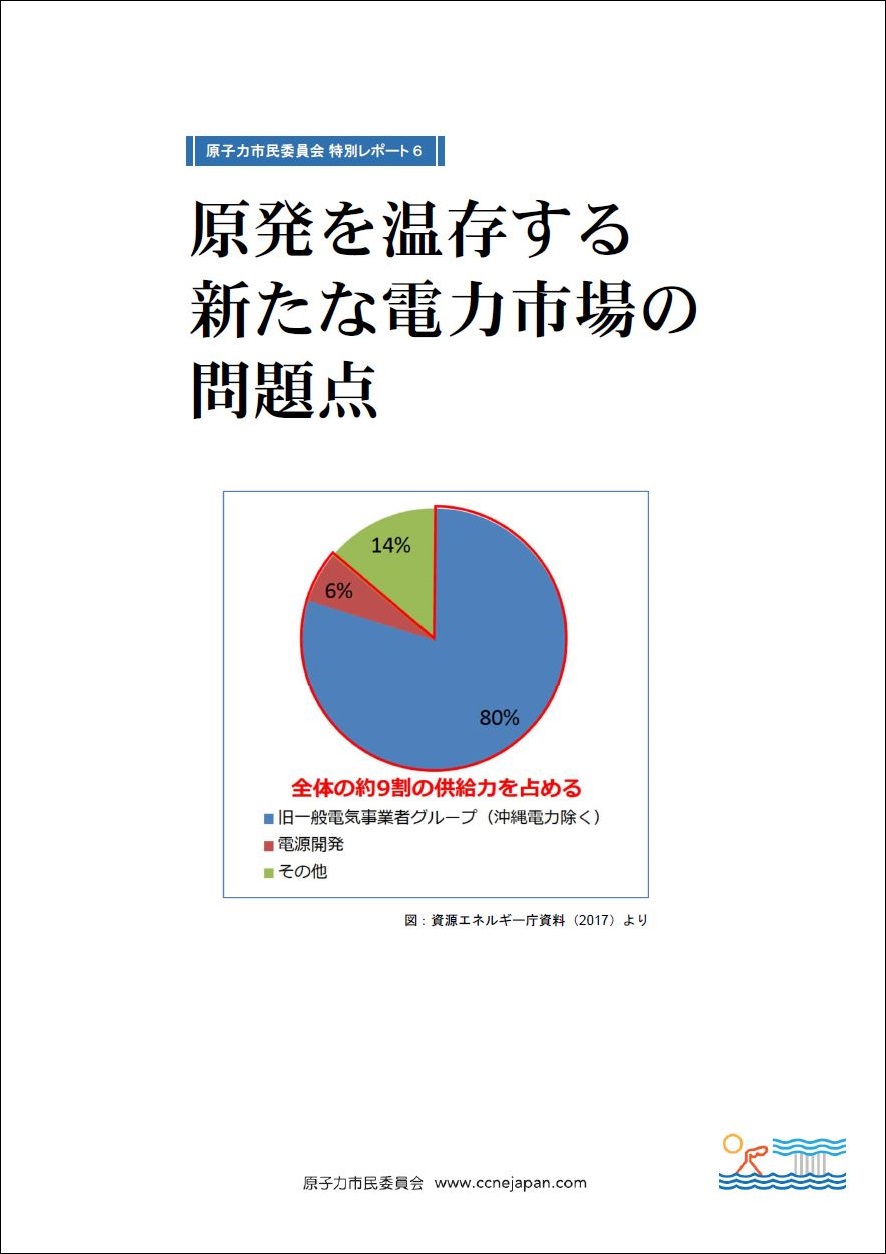
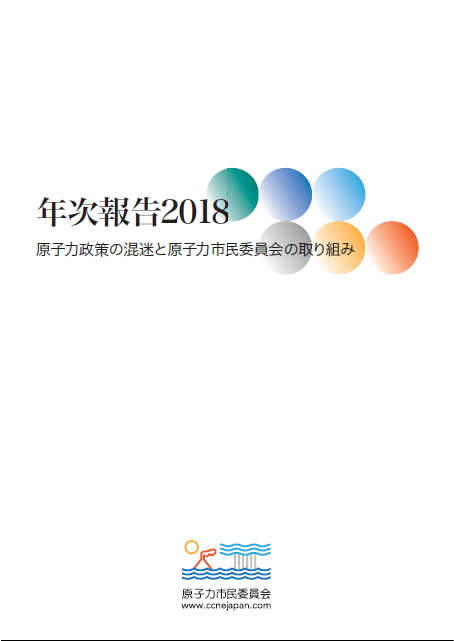
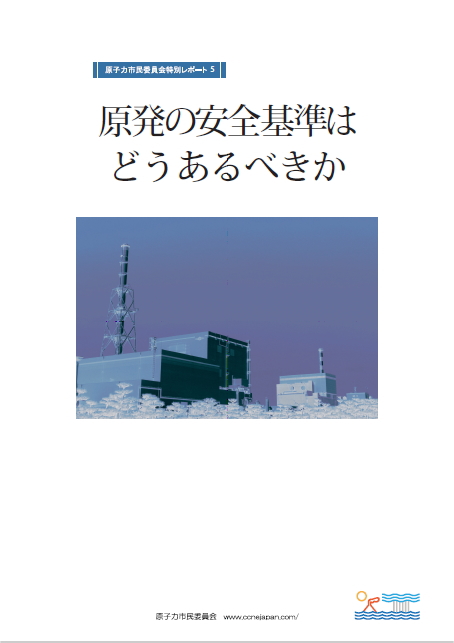
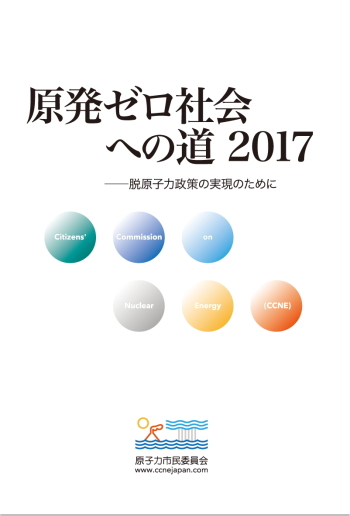
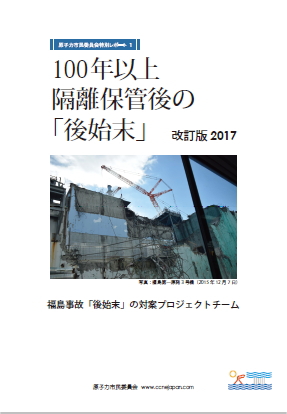
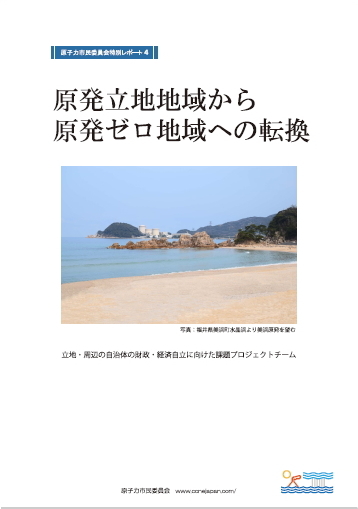
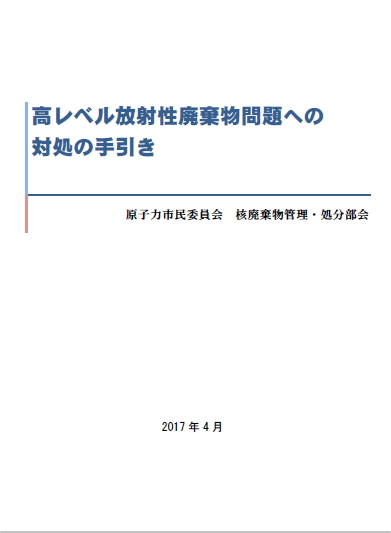
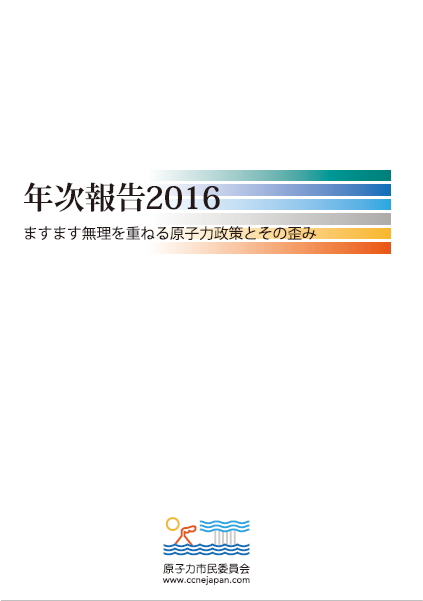
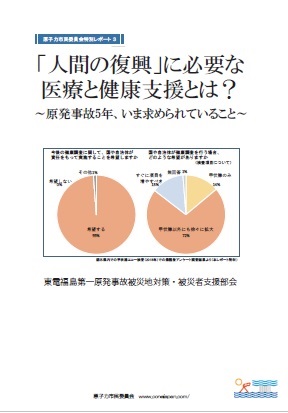
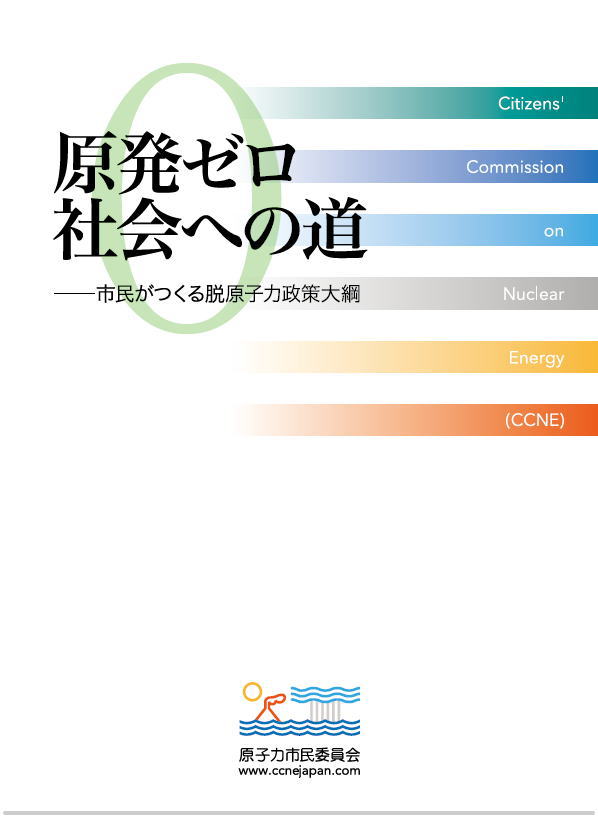 『原発ゼロ社会への道――
『原発ゼロ社会への道――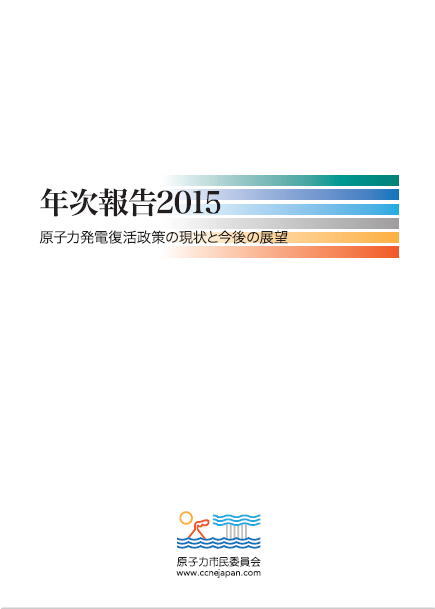
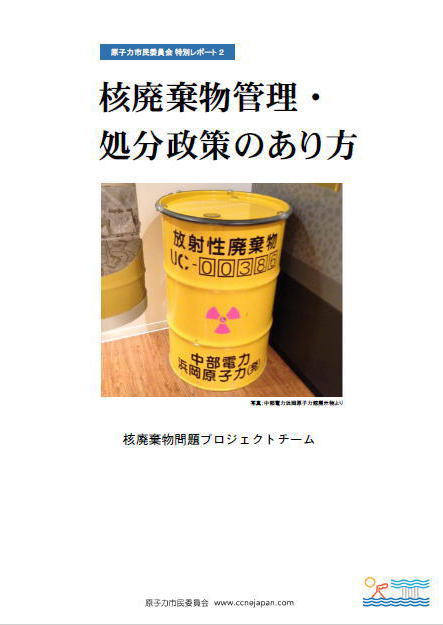
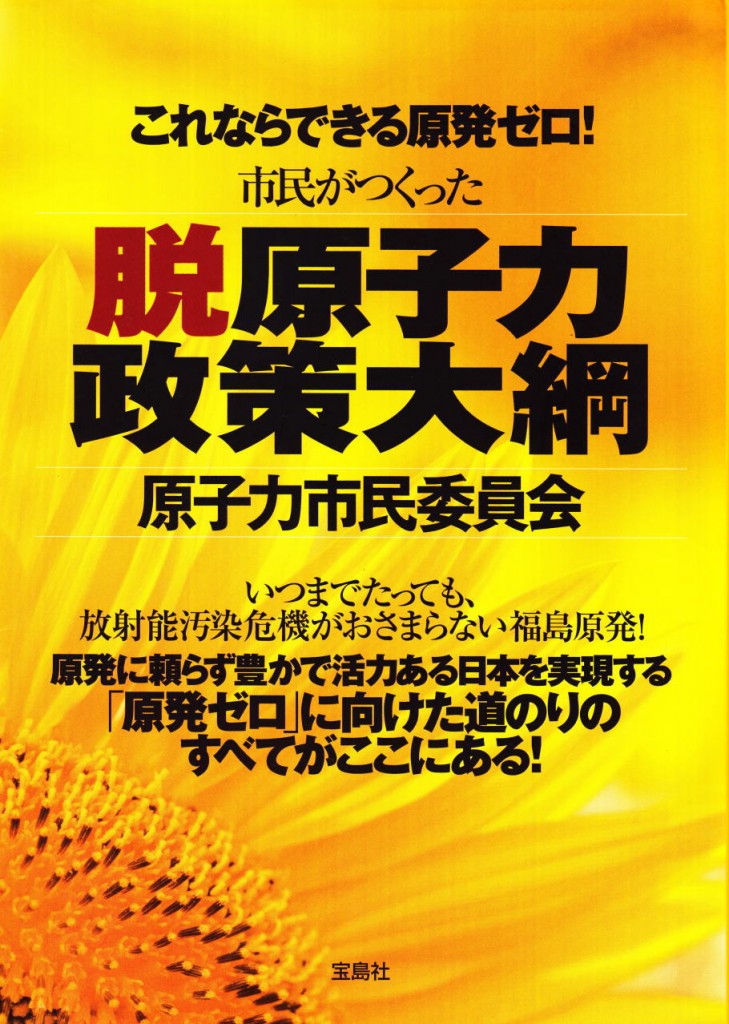 『これならできる原発ゼロ!
『これならできる原発ゼロ!